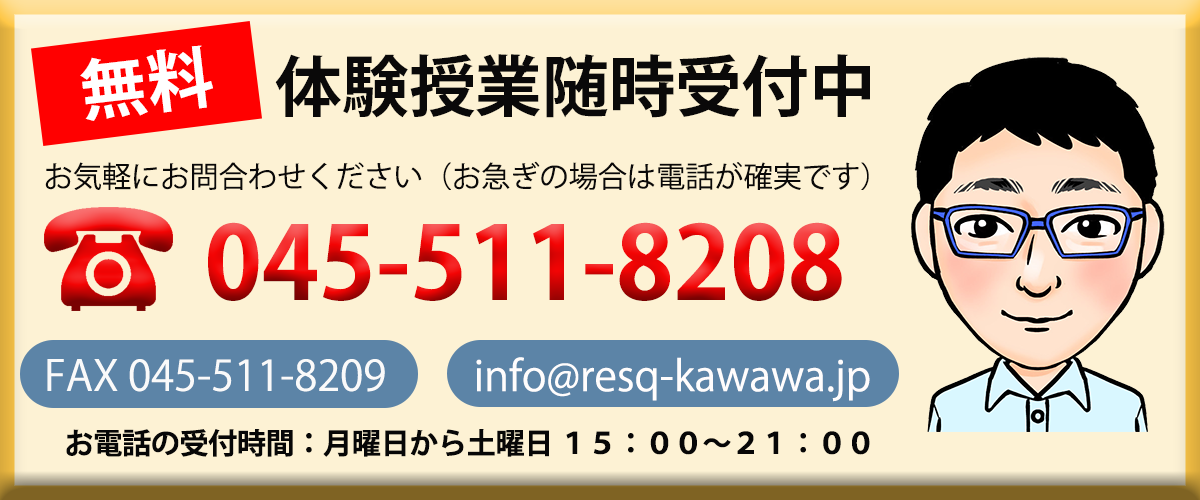中学生は今、定期テストの真っ最中です。
ここで塾生のAさんのお話をしたいと思います。
Aさんは中学1年生の頃に入塾してきました。
性格はおとなしく、どちらかというと引っ込み思案なタイプでした。
ですので、授業中に質問する回数も他のお子様より少なかったです。
変わり始めたのは中学2年生の夏ごろでした。
その時点でAさんには行きたい高校が明確に決まっていました。
そして、高校入試の模擬試験にて志望校へどれだけの努力が必要か知ったのです。
このことをきっかけに彼女の中で勉強への意識が変わったのでしょう。
それからの定期テストでは右肩上がりでテストの点数や内申点が上がっていきました。
この話の要点は”なんのために自分は勉強をしているのか”をどれだけ意識しているか、ということです。
少なくとも勉強を”無理やりやらされている”と感じているお子さまと比べてみればどちらが望ましいかは明確です。
この意識の差が勉強の質にも大きく影響してきます。
普段の勉強やテスト対策の時に問題を解いていて、間違えてしまった問題があったとします。
その時、意識が低いお子様は丸付けをして正答を書いて終わり、ということが多々見られます、
対して意識の高いお子様はこの問題を”なぜ”間違えてしまったのかを考えています。
その原因がケアレスミスなのか、そもそも問題の意図を理解できていなかったのか。
同じ不正解でも原因は様々です。
つまり自己分析をしなければ真の原因、そして解決策は見えてきません。
人は間違いを必ずします。
それは保護者の方々やお子さまに関わらず人である以上避けられません。
ではその間違いをしてしまったときにどう対応するのか、そこが今後の成長への分かれ目です。
私は塾生の中でも特に中学生・高校生に対して、勉強だけでなく上記の話をよくします。
学生の本業は勉強です。
しかし、勉強が好きというお子さまはまれでしょう。
であれば、”嫌だけれどもしなければいけないこと”への取り組み方を大人が子供へ教える必要があると思うのです。

.jpg)